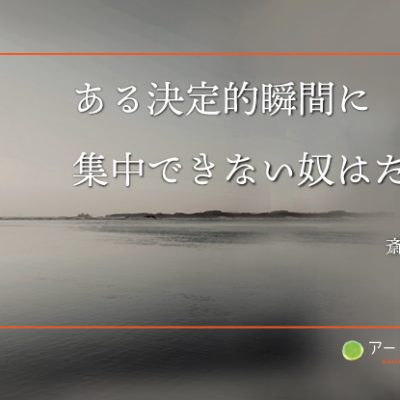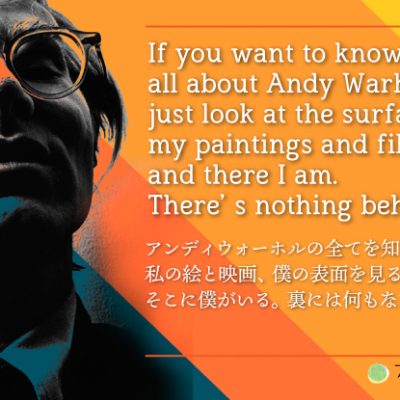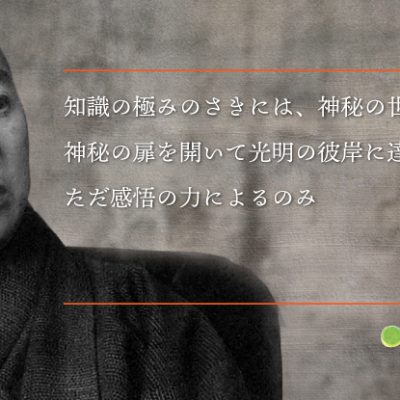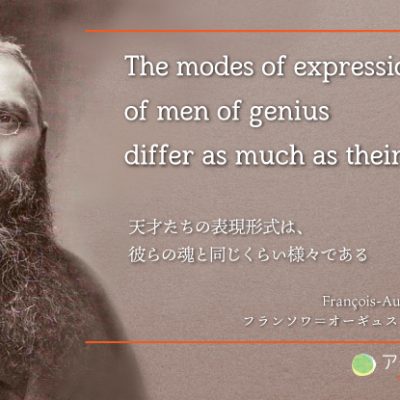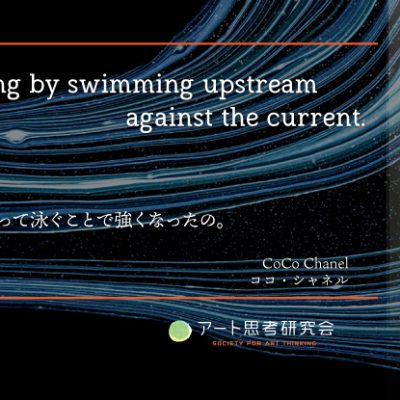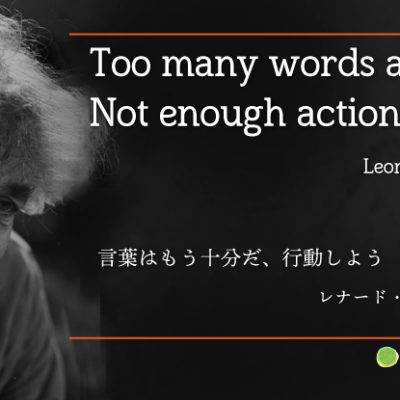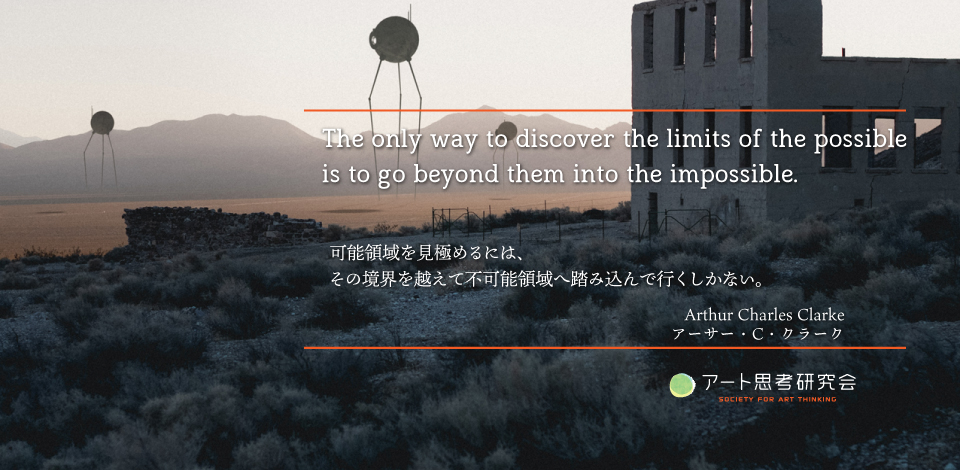
6月は、私が大好きなSF作家、アーサー・C・クラークさんの言葉を紹介します。
クラークさんの作品を読み始めたのは、イリノイ大学在学中の頃です。
『2001年宇宙の旅』に出てくるHALが、イリノイ大学アーバナ・シャンペーンで作られたと出てくることから、情報科学の学生の間では、この本はMUST READ(絶対読むべき本)として紹介されていたからです。
「なぜHALはアーバナで生まれたのか」というレクチャーがYouTubeにアップされているので、ご興味のある方はそちらを見てください。
学生時代に、『2010年宇宙の旅』と 『2061年宇宙の旅』 を読み、卒業後、社会人になってから、 『3001年終局への旅』を読みました。2061年は2001年を読んだ時ほどの面白さがなく、かなりがっかりしたのですが、3001を読んで、あぁ、人の未来ってやっぱりこうなんだろうなぁ~と、妙な納得感がありました。気になる方は是非4部作を読んでみてください!
前置きが長くなってしまいました。
今日のクラークさんの言葉は、BCGに勤めていたころに、似たようなことを先輩が言っていたので、「人って同じようなことを言うな!」と思い、覚えている言葉です。
可能領域を見極めるには、その境界を超えて不可能領域に踏み込んでいくしかない
アーサー・C・クラーク
20代半ばの私は、自分がどこまでやれるのか、どこまでがやれないのか、仕事においても、歌においても、いつも悩んでいる状態でした。
背伸びをしていればいつの間にか背は伸びる
と、その先輩によく言われたのですが、
溺れたことのない奴は、どこまでやったら溺れるかがわかっていない。
一回溺れてみろ。
とも言われたことがあります。今言ったらパワハラになりかねない言葉ですが、この先輩、とっても愛ある方だったので、「なるほど~」と私は思ったのでした。
溺れるってどういうことだろうと思った私は、プールではなく、知識の海に飛び込んでみました。
まったくやったことのない領域のプロジェクトに手をあげて入れてもらい、先輩方には相当なご迷惑をおかけしたのですが、わからないことにまみれて、あっぷあっぷの状態にすぐになりました。
溺れるまでやってみて、「私はここまではできる。ここからはできない」という線が明確に見えたのでした。
わからないことがわからない
という段階から、わからないことがわかった、じゃぁどうやったらそれを身につけられるだろうか。どうやったらその中で付加価値をつけていけるようになれるだろうかというところまできたのでした。
それがわかると、自分が工夫する余地はたくさん出てきます。
工夫に迫られれば人は創造的になります。
不可能な領域に飛び込んでいくことで、自分の可能領域の広さがわかるし、どうしたら創意工夫することができるのかにも気づくことができるんだなぁと思った出来事でした。
実は同じことが音楽の演奏においてもいえるというのは、その後何年もしてから気づくのですが、たぶんどの領域においても同じなのでしょう。

戦略・事業開発コンサルタント、声楽家、アート思考研究会代表幹事
イリノイ大学在学中に、世界初のウェブブラウザ―であるNCSA Mosaicプロジェクトに参加後、世界初の音楽ダウンロードサービスやインターネット映画広告サービス等の数多くの新規事業を立ち上げ、インターネット・エンジニアのキャリアを重ねる。ボストン・コンサルティング・グループの戦略コンサルタント、GE Internationalの戦略・事業開発本部長、日本IBMの事業開発部長を歴任。2012年に独立し、戦略・事業開発コンサルティングを行う会社Leonessaを設立。明治大学サービス創新研究所客員研究員。声楽家としても活躍し、TV朝日「題名のない音楽会」では「奇跡のハイヴォイス」と評される。国際芸術連盟専門家会員。
子どもの不登校をきっかけに、大学で心理学を学び、認定心理士、不登校支援カウンセラー、上級心理カウンセラー、Therapeutic Art Life Coachなどを取得、心のレジリエンスとアート思考の融合を模索中。
著書
- 『ミリオネーゼの仕事術【入門】』
- 『自由に働くための仕事のルール』
- 『自由に働くための出世のルール』
- 『考えながら走る』など多数。