音楽は得意だったけれど、美術はちょっと苦手。
絵に関しては描くのも見るのも苦手で、話題の絵画作品も「どこがいいのかわからない」と思うこともよくあります。それでも、2〜3カ月に1回は美術館に出掛けます。
それは、音楽の幅を広げるために、人間の幅を広げるために、美術館へ行きなさいと、当時の先生から指導されたことがきっかけです。
毎年、年初に行きたいと思う美術展や、先生から勧められた美術館をリストアップし、「なぜ行きたいのか」、「そこで何を見たいのか」という事前準備をして、展覧会へ行き、そして感じたことをノートに記しています。
私は先生から指導された方法を守って、アートを見てきたけれども、専門にやってきているわけではないので、自分がやっていることがあっているのか、本当のところはどうなんだろう?
そういつも感じていたので、この本を手に取りました。
子供の絵はなぜいいのか?絵はどうやって見てどう評価すればいいのか?美術批評家・椹木野衣は、どのようにつくられ、どんなふうに仕事をして生きているのか?美術批評の第一人者が、絵の見方と批評の作法をやさしく伝授し、批評の根となる人生を描く。著者初の書き下ろしエッセイ集。
内容 Amazon.co.jpより
目次
はじめに
感性は感動しない
Ⅰ 絵の見方、味わい方
Ⅱ 本の読み方、批評の書き方
Ⅲ 批評の根となる記憶と生活
「あなたは感性を持っていますか?」
「岡本太郎は感性について次のように言っている。
『感性をみがくという言葉はおかしいと思うんだ。
『感性は感動しないー美術の見方、批評の作法』より
感性とは、誰にでも、瞬時にわき起こるものだ。』
中略
『はっきり言うが、芸術に技は必ずしも必要ではない。芸術に必要なのは、圧倒的に感性である。』
と、冒頭の『感性は感動しない』というエッセイから、「あなたは感性を持ってますか?」とガンガン問いかけてくるのに、圧倒され気味で読み始めました。
しかし、このエッセイの後半では、『芸術における感性とは、あくまでも見る側の心の自由にある。決して、たかめられるような代物ではない。その代わり、貶められることもない。その人がその人であるということ、それだけが感性の根拠だからだ』と、個人の体験や経験、そして、自分の中身をどれだけ知っているかが感性を形づくるものだと、「アート」を見るヒントを与えてくれます。
そして、椹木氏なりの絵の見方、味わい方を提示してくれるため、それにぐいぐいと引きずり込まれていきました。が、東京の散歩の仕方とか、ツイッターの書き方やスマホとのつきあい方など、「感性とどんな関係があるのだろう?」と思う内容もあり、これらの「かたまり」を彼はどう捉えてほしかったのか? いや、そもそも捉えるのではなく、感じることが大切なのか? と、読後に頭の中でいろんな考えや思い、感情が交差しうろたえてしまいました。
もしや「これが彼が狙っていたことなのか!?」
感性を通じて自身の中を覗き込もう
今話題となっている「アート思考」をはじめとした「〇〇思考」は、取り入れたらすぐにイノベーションにつながるわけでは決してありません。それらの思考の本質を理解して、例えばアート思考であれば、自分の生活や、そしてビジネス、さらにコミュニティや社会に、どのように取り込んでいくのかを考え、実践していくことが大切です。
アート思考は、アーティストたちが頭の中にあるアイディアから作品を生み出す、ゼロからイチを生む思考プロセスを辿り、創造性についてのヒントを得ることです。アーティストたちが社会に対して提起する問題意識は、自分と、そして、社会と向き合い、思考を掘り下げていくことでしか、生まれてきません。
著者はアートを見ることは「感性を通じて自身の中を覗き込む」のだといいます。感動という言葉を使うのではなく、どこに、何に感動したのか。掘り下げて感じたものの正体を突き止めていくこと。これは、アートだけではなく、すべての物事に応用できる考え方ではないでしょうか。

戦略・事業開発コンサルタント、声楽家、アート思考研究会代表幹事
イリノイ大学在学中に、世界初のウェブブラウザ―であるNCSA Mosaicプロジェクトに参加後、世界初の音楽ダウンロードサービスやインターネット映画広告サービス等の数多くの新規事業を立ち上げ、インターネット・エンジニアのキャリアを重ねる。ボストン・コンサルティング・グループの戦略コンサルタント、GE Internationalの戦略・事業開発本部長、日本IBMの事業開発部長を歴任。2012年に独立し、戦略・事業開発コンサルティングを行う会社Leonessaを設立。明治大学サービス創新研究所客員研究員。声楽家としても活躍し、TV朝日「題名のない音楽会」では「奇跡のハイヴォイス」と評される。国際芸術連盟専門家会員。
子どもの不登校をきっかけに、大学で心理学を学び、認定心理士、不登校支援カウンセラー、上級心理カウンセラー、Therapeutic Art Life Coachなどを取得、心のレジリエンスとアート思考の融合を模索中。
著書
- 『ミリオネーゼの仕事術【入門】』
- 『自由に働くための仕事のルール』
- 『自由に働くための出世のルール』
- 『考えながら走る』など多数。

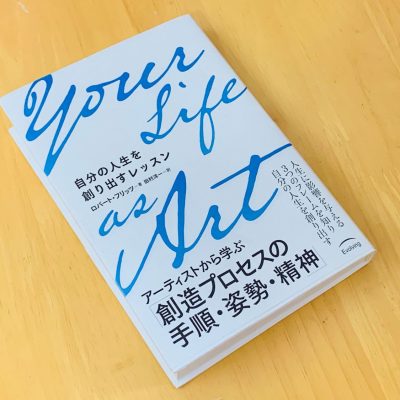

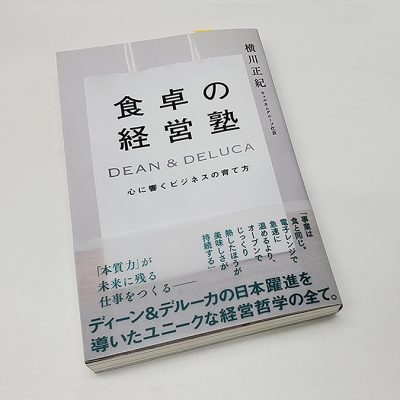
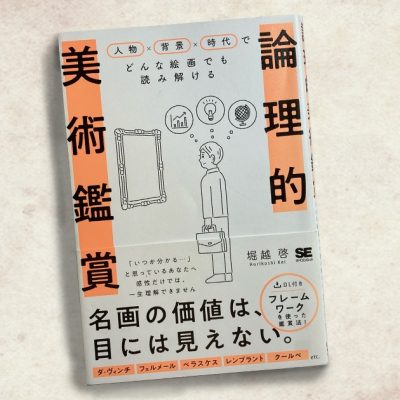
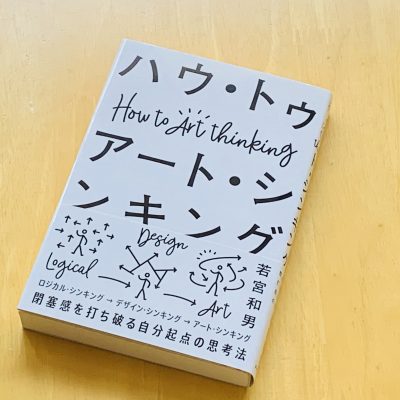
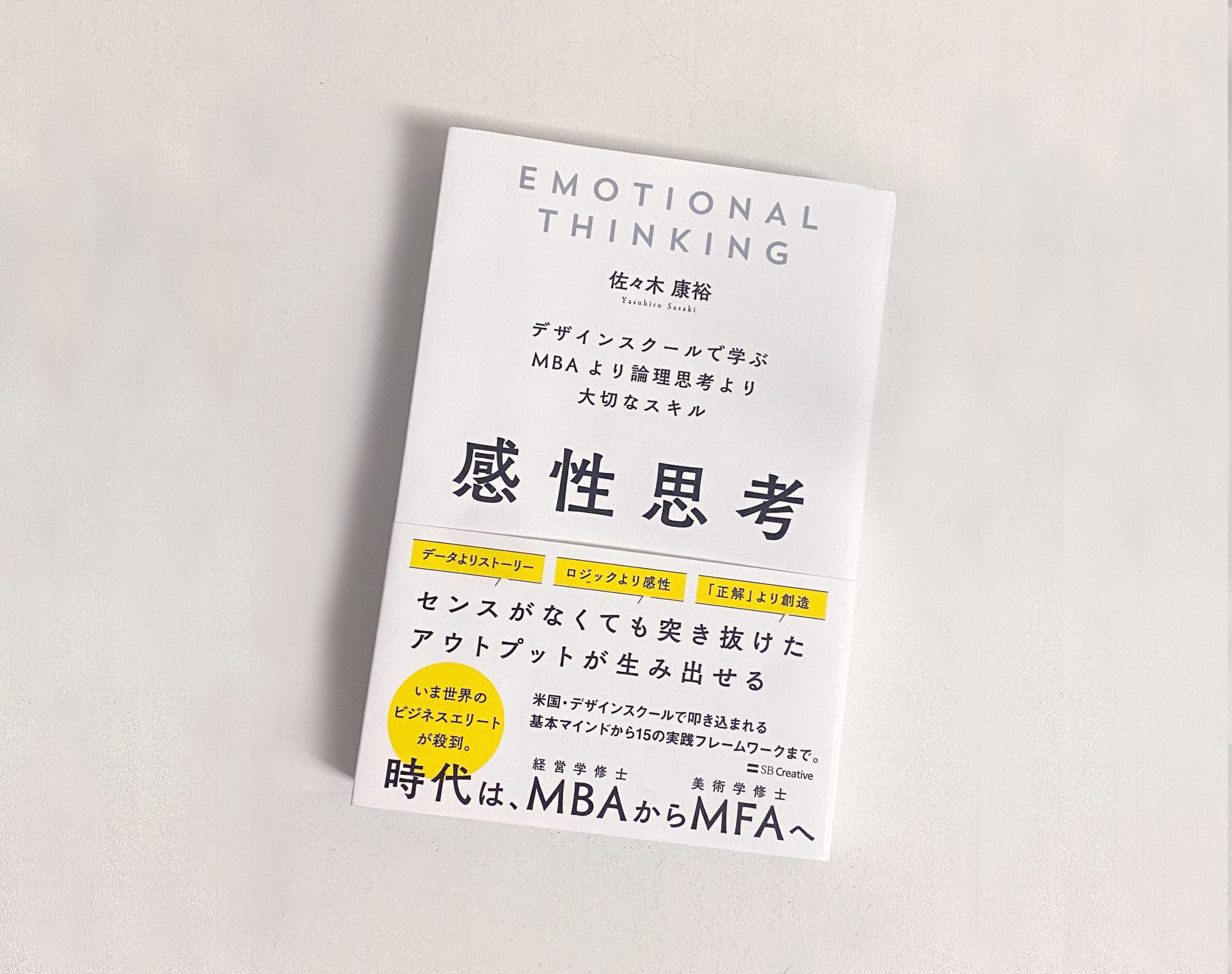
-400x400.jpg)