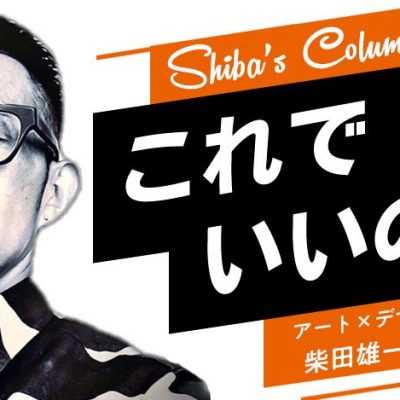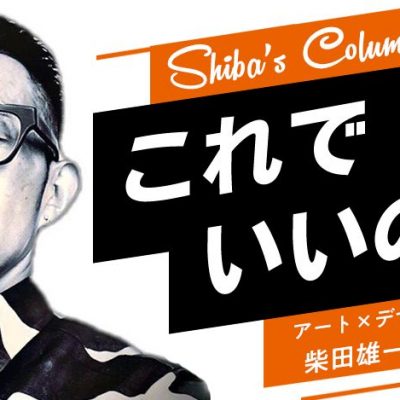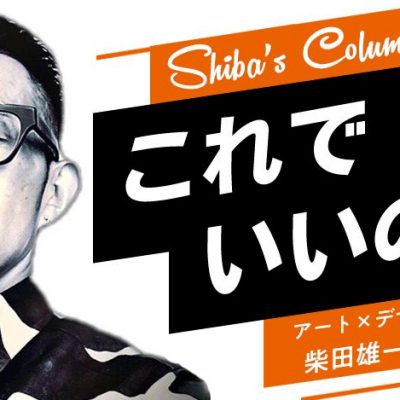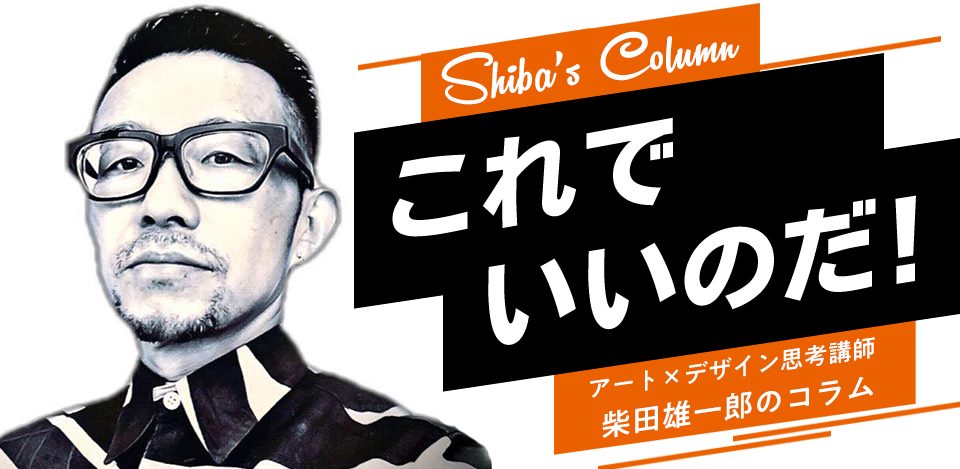
昨日、著者の永井さんからお声がけをいただきZOOMでお話ししました。永井さんは。2013年経済産業省に入省。主に、知的財産政策や法律改正業務に携わり、その後、ボストン コンサルティング グループに入社し、大企業の新規事業立ち上げや営業戦略等のプロジェクトに従事してきました。
とても共感したのはアート思考だけでもデザイン思考だけでも、ロジカル思考だけでもダメで、いかに3つの思考のバランスを柔軟にマネージメントできるかというところでした。
”実は、これまで様々な起業家と接してきた経験上、このデザイン思考とアート思考が重なり合う(統合する)地点が起業のスイートスポットだと気がついたからです”これを著者は「統合思考」と呼んでいます。
また、生産性中心だった頃は価値が定量的に数値で測れました。生産の効率化や広告の費用対効果といったように効果測定が明確ですが、創造性を中心に据えると指標となるものが定性的になって、なかなか成果が見えにくいという問題もあります。その点もとても共感しました。多くの起業家や新規事業の現場を経験していくとぶち当たる壁です。
永井さんの本には<トレードオフ>という言葉がよく出てきます。
トレードオフとは、「両立できない関係性」を示す言葉として使われています。 言い換えると、一方を尊重すればもう一方が成り立たない状態のことです。売上←→単価の様に、売上を上げるには単価を下げる。という構造から一方を尊重すればもう一方が成り立たない状態を超えたところにある答えを導き出すのが創造性で、その相反する二項対立する様な概念を統合して新しい正解(価値)を作り出すことだと説明しています。”一見して非合理的な部分を全体合理性に転嫁していくことが、長期的な競争優位性を維持することにつながる”ご本人は「仕事も頑張りたいし、子育てなどの家庭も大事にしたい」という内発的な動機から「仕事」と「家庭」のトレードオフを解消するという人生の課題から「創造力」を仕事と人生のテーマにしたそうです。
この本の中では創造性を生み出す思考を「アナロジー思考」としています。”類似する他の物事と結びつけて新しい発想をしたり当該物事の理解を深めようとしたりする思考法で、他の人には思い付かないような新しい結合を生み出したり、発想の飛躍を起こす思考法として説明しています。
クレイトン・クリステンセンは「こと創造性に関する限り、生まれよりも育ちなのだ・・・イノベーションに必要な能力のほぼ3分の2が学習を通じて取得できる」といっています。この本のタイトルにもあるように、創造性は誰でも伸ばすことができるということをたくさんの事例からわかりやすく解説してくれています。
まさに答えの見えない時代に新しい正解を創造するという点でアート思考と通じる概念です。

1966年生まれ、日本大学芸術学部 演劇学科卒業。
アート×デザイン思考講師/ トヨタ自動車から内閣府まで新規事業開発専門のフリーエージェントを経て公益代理店 一般社団法人i-baを設立。熊本大学「地方創生とSDGs」/京都芸術大学「縄文からAIまでのアート思考」非常勤講師。地域デザイン学会 参与。FreedomSunset@江ノ島主催。DJ/トランペッター。逗子アートフェスティバル2017・2020プロデューサー。
◆アート×デザイン思考入門と実践
アート思考の入門編と実践編をスキルシェアサイト「ストリートアカデミー」でZOOMによるオンライン開催をしています。
◆いつでも学べるUdemyのオンライン講座
2時間を超えるアート×デザイン思考のセミナーをオンライン学習サイトudemyに公開しました。
◆シバのツイッターはこちら(お気軽にフォローしてください)