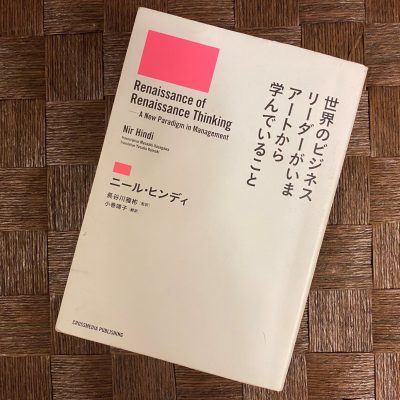本書は、いわゆる”アートシンキング”のHow to本ではありません。
ビジネスですぐに試せる方法論をお探しの方に本書は適切ではないでしょう。
ビジネス上、ブレークスルーを必要とする人が、自らのアートとの関わり方(元来アートに興味があった、自分も作品を作っていた、コレクターであるなど)の中で、それぞれの方向性を見出した事例が複数の著者の共著によって綴られています。
著者らは、「アートと関わること」のメリットとそれを導く力(本書では”アートパワー”と呼んでいる)を4つに分類しました。
4つのアートパワーとは、「問題提起力」「想像力」「実践力」「共創力」です。
著者らは、彼/彼女らの仮説的推論によって設定されたと思われるこの4つのパワーとその相互関係を、先に挙げた事例や著者らによるリサーチによって裏付けようとしています。
読者がすでに“アート”に興味を持っていてこの本を手にするならば、自分なりの活用方法のヒントがあるかもしれません。
前半は、そんな人に読んでもらうためのビジネスサイドでのアートとの付き合い方の事例集、後半では理論づけを試みます。
<目次>
Ⅰ. アート・イン・ビジネスとはなにか?
1. アート・イン・ビジネスのしくみ
2. アートでブランディングする
3. アートでイノベーションを起こす
4. アートで組織を活性化する
5. アートでヴィジョンを構想する
6. アート・イン・ビジネスの時代へ
II. アート・イン・ビジネスの理論的背景と実践法
7. アートとはどのようなものか
8. アート・イン・ビジネスに効果はあるのか
9. アート・イン・ビジネスの実践法
10.アート・イン・ビジネスが未来を描く
アートの見方はさまざま
本書は複数の著者による共著であるため、アートとビジネスパーソンとの関係が各人の異なる人脈/視点でオムニバス風に描かれているのが特徴です。
ただ、その受け手も含めて行われるアートの解釈はとても自由です。
本書では、この自由な空間を歩くための地図が冒頭で示されます。
半ば強引ともいえる二項対立を例にとり、あるいはいかにもコンサルタントという風情で二軸マトリクスによる整理を行うのは、読者の理解を促進するためにメリハリが必要だったということなのだろうと思えます。
読者はその構図に囚われることなく、示される幾多の事例から帰納的に何かを感じるのがよいのではないかと思いました。
アートは自由ですから。
本書の“アート”と本書が語らないアート
本書では現代アートを素材として次のような“アート”との付き合い方が語られています:
a. アート作品を商材として扱う
- アート作品の持つイメージを借りて企業のブランディングを行う
b. 現代アート作品との接触面積を増やす
- 従業員の感受性の増大を狙う
c. 作品鑑賞の場の共有や、アーティストとの協働をコミュニケ―ションの場として使う
- 異なる種類の人たちとの議論の場を創設し、視点を増やし新たなものの考え方を得る
一方、本書では、ビジネスプロセス内でアート思考を手法として使うことで、直接的リターン(なんらかのブレークスルーなど)を期待する事例は取り上げていません。
これが冒頭で書いた、「手法が欲しい読者」には本書が適切でない、という所以です。
a. アート作品を商材として扱う
正直、これもアート・イン・ビジネスの範疇なのか、と驚きました。
自社が扱う商材にアート作品を加えることで文化的側面を持っていることを顧客にアピールするというもので、商材はアート作品でなくてもよいかもしれません。
ただ、これが範疇かそうでないのかを問い、本来自由であるアートに枠組みを与えようとすること自体、アートに対する態度としては不適切なのかもしれません。
b & c. アート作品・アーティストと関わる
本書の事例は、アートに造詣が深い経営層が、組織としての物事への「感度」を上げていくために、従業員を含むステークホルダがアート作品と接し、それについて考える癖をつけ、他人と意見交換をし、かつまた、アーティストとの協働をするなどの機会を設けるというものです。
本書では現代アートにフォーカスしていますが、まったく同様の試みは音楽や、自ら表現をするパフォーマンスなどでも行われており、目利き力を養うことだ、と言っている学者もいます。
アート・イン・ビジネスを理屈で捉える試み
本書ではここで、同書の冒頭に示されたアートの効用分類に論理的な裏付けを与えようと心理学の測定尺度を取り出し、一般企業を交えたリサーチを実施しています。
残念ながら、結果は、アートと付き合うことが、定量的に目的の指標に影響を与えた、と証明するには至りませんでした。
アートを活用してきた事例各社の試みは、それぞれ異なる角度からアート作品やアーティストと従業員との接点を持たせることで、その人々の感度、違いを感じ取る閾値の変化を起こさせたものでした。
それぞれのアプローチでは、アート作品、アーティストとの関わり方は実に自由なのだと気づかされます。型にはめない、それこそがアートとの付き合い方なのだと。
仮説的推論を事例から実証しようという本書の試みが、かえってアート自体が持っている自由奔放さ、扱いの自由さを認識させる結果となっていることを大変興味深く思いました。
アートと自分、アートとビジネスの関係を読者自身はどのように捉えるのでしょうか。このような問いの喚起こそ、理論的な解き明かしに敢えて挑戦した本書の意味であったのだろうと思います。

Creative Research™ Consultant
横河電機株式会社
ファームウエアエンジニアから始まり、SEや研究開発企画などを経て、徐々に商品開発フローの上位へ上位へと仕事を移し、現在はインハウスデザイン部門に勤務。
デプスインタビューなどでユーザを徹底的に知るための方法論を展開すると同時に、最も重要だと信じる”開発者の意志を汲みだす対話”にも重点を置くCreative Research™を提唱している。
あらゆる開発プロジェクトに横断的に関わるデザイン部門に身を置くことで、効果的にコミュニケーションを図り、哲学シンキング、デザイン思考、システム思考、LEGO® SERIOUS PLAY®などを駆使して、ユーザの心に共感し、開発者の想いに迫る。
“Act without authority”が信条。