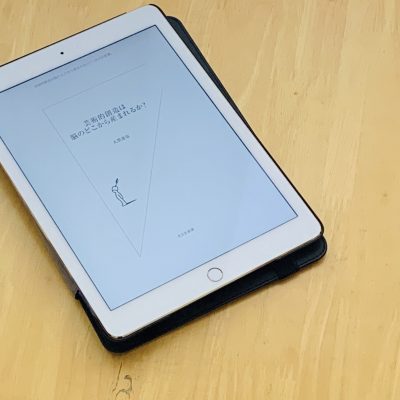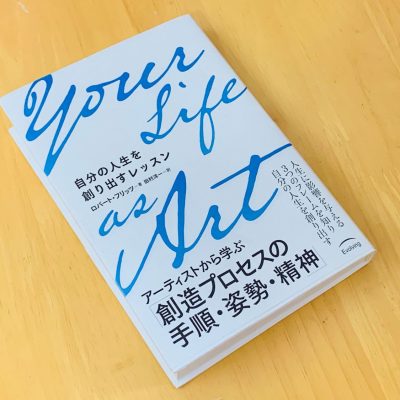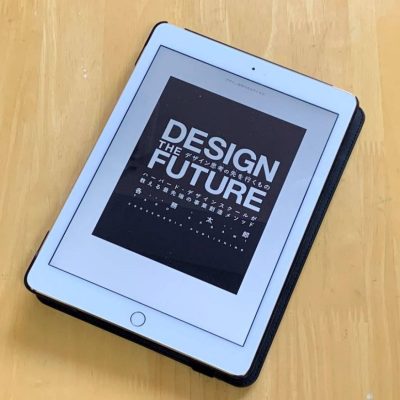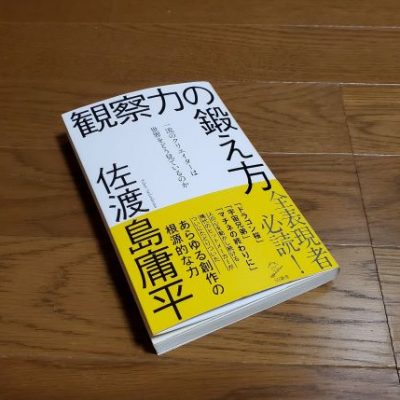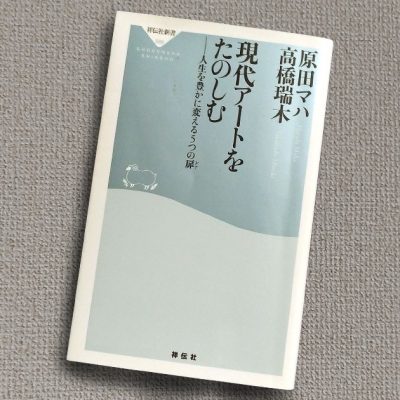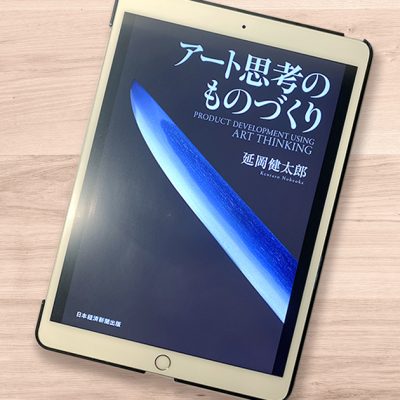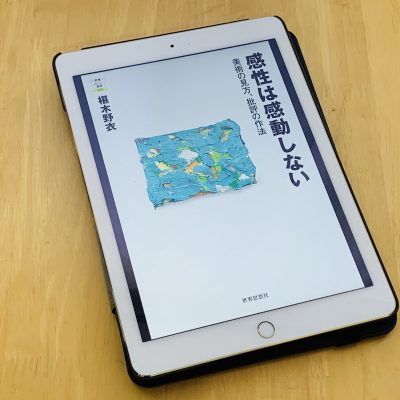英語の原題は『THE DOODLE REVOLUTION(ドゥードル革命)』です。
タイトルのDOODLEは、「ラクガキ」と訳されていますが、もっと違う意味も持つようです。
まぬけ・ばか・汚職政治家・嘲笑・詐欺など、あまり良い意味の言葉ではないようですが、本書では「思考の助けとなる目印を好きなように描くこと」と定義しています。
そのラクガキを、ビジュアルコミュニケーションのツールとして活用し、情報・思考の整理、アイデアの共有、そして集中力とリラックスを促進するなど、ビジネスの役に立つ活用方法を教えてくれる良本です。
著者のサニー・ブラウンが、TEDでラクガキの有用性について語ったスピーチがきっかけとなり、話題となった本です。
副題は、『「ドゥードル」革命-ラクガキのパワーが思考とビジネスを変える!』。
地球にいる人類ほぼ全員がやっている、学校や会議中の “ラクガキ”“いたずら書き”の中に、誰も思いつかないようなアイデアが埋まっているかもしれないし、ビジネスを活性化させるかもしれないとなれば、ラクガキを活用しないわけにはいきません!
ビジュアルを活用することで、クリエイティブな発想・思考を促進する方法が豊富に記載されています。
新しい何かを創り出したい人には、ぜひ、このラクガキ活用方法を読んでもらいたいと思います。
目次
第1章 ラクガキとは考えること
第2章 ドゥードルの画期的効果:パワー・パフォーマンス・プレジャー
第3章 ドゥードル大学:ビジュアル言語の基礎を学ぶ
第4章 インフォドゥードル大学:ビジュアル・シンキングの達人になる
第5章 インフォドゥードルの活用:グループの思考法を変える
第6章 ビジュアル・リテラシーの向上をめざして:ドゥードル革命を実行せよ
絵を描いて理解する
この書評を書いている私の職業は、グラフィックデザイナーなので、自分の気づきやアイデアを絵に起こすことは自然なことでした。
デザイナーとして大切なもののひとつは、クライアントの要件を的確に理解してまとめることです。
抽象的なクライアントの思いや、目に見えない案件の構造をビジュアル的に理解し、共有するには、絵を描くことがとても重要でした。
その記憶から考えると、たしかに「ラクガキ」は、情報を整理し、思考を促進してくれます。
無知に対する武器として、複雑な問題に対処するツールとして、洞察を深める瞑想として、発見を求めるゲームとして……そうした可能性がすべて、誰にとっても身近な「ドゥードル(ラクガキ)」に秘められている
『描きながら考える力 「ドゥードル」革命-ラクガキのパワーが思考とビジネスを変える!』前書きより
ビジュアル言語
アメリカの美術教育の研究者ヴィクター・ローウェンフェルドの『美術による人間形成』によると、子どもの造形の発達は、世界共通で、その発達段階は主に5つに分けられるそうです。
なぐり描き→図式化前→図式化→写実傾向の芽生え→擬似写実的
これが2歳くらいから13歳くらいまでの子どもの絵を描く発達の段階です。
子どもたちは、誰かに教えられることなく、文字よりも先に絵を描き始めます。
どんな子どもでも、自分の気になること、思い浮かんだことをママに伝えるために、自然に絵を描き始めます。
絵を描くことで、ものごとを認識し、共有することができるのは、人間にしかできない特異な能力です。
また、イスラエルの歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリ氏は、『サピエンス全史』で、人類にはいくつかの進化のうえでの革命があったと言います。
そのうちのひとつが「認知革命」です。
虚構を信じる能力のことを言います。
絵に描かれた動物は、本物ではありませんが、その絵を見ることで、本物の動物を思い描ける能力を身につけたということです。
つまり、人類は、視覚を通して情報を共有し、思考を整理する力があるということになります。
言葉や文字ではなく、視覚を通してコミュニケーションを取る言語が存在しているはずです。
それを「ビジュアル言語」と本書では定義をして、その活用方法を提唱しています。
ラクガキの効果
本書では、ビジュアル言語のことを「ラクガキ」と名付け、その効果は以下のものだと説明しています。
・POWER
(心の拡張・理解 情報の保持、呼び起こし 情報の理解 洞察を深める 創造力の向上)
・PERFORMANCE
(大きなイメージの共有 全員を夢中にさせる 創造的、戦略的、戦術的思考 改革の奨励と問題解決 会議の効率化 記憶の共有とビジュアル記録)
・PLEASURE
(集中 リラックス 可能性)
『描きながら考える力 「ドゥードル」革命-ラクガキのパワーが思考とビジネスを変える!』P. 29
POWERについて
イギリス、プリマス大学の心理学者ジャッキー・アンドレードは、被験者に退屈な録音を聞かせる実験を行い、ラクガキをしながら聞くグループと、ただ聞くだけのグループに分けた。そして録音の内容をどれだけ記憶しているかテストを行うと、驚くことに、ラクガキをしていたグループが保持し、呼び起こした記憶は、聞くだけのグループより29パーセント多かったのである
『描きながら考える力 「ドゥードル」革命-ラクガキのパワーが思考とビジネスを変える!』p. 30
ここでは、ラクガキをすることで、そうでない時よりも認識する力を高めることができると、事例がいくつか紹介されています。
記憶にとどめる事例のほかに、思考する際も手を止めて考えるよりも、手を動かして考えるほうが効果が出ると書かれています。
手を動かすことにより、身体を刺激し、思考回路に良い影響を与えることができるからです。
PERFORMANCEについて
グループでラクガキをすれば、大勢の人が同時に、より詳しく、大きなイメージを思い描くことができる。言葉に頼って、ひとりひとりの不完全な視点を知るよりも、ラクガキを共有し、話し合うテーマごとにビジュアル化するほうが、グループの合意を形成しやすい
『描きながら考える力 「ドゥードル」革命-ラクガキのパワーが思考とビジネスを変える!』p. 38
たしかに会議の場面を思い返すと、ホワイトボードをうまく使うのが有効です。
現在の状況を図解し、相関関係を視覚化し、グルーピングをしながら、全員の意識をホワイトボードに集中させて議論してもらう。
全員が同じ方向を向いて意見を交わすことができることを、私たちは体感してわかっているようです。
進行役がしっかりとビジュアルを駆使して会議をすれば、かなり充実した議論ができるということです。
PLEASUREについて
ただ静かに座って、紙の上でペンを動かすこと。ラクガキをするうちに、目標や結果ばかり追い求めているのではない、遠回りの良さに気づくだろう。心の動きに合わせて曲がりくねった線を描くこと、あてもなく動いて楽しむこと、いつまでも好きでいられるただひとつの物事に集中することには、価値があるのだ
『描きながら考える力 「ドゥードル」革命-ラクガキのパワーが思考とビジネスを変える!』p. 42
ここでは、ひとつのことに集中することで、リラックスの効果があると伝えています。
ただし、PCやスマホのスクリーンは、否応なしにその画面に集中させてしまうのでおすすめできません。
それは、強制的に集中力を作り出しているので、かえって疲労を引き起こすことになるのです。
手を動かすラクガキで「フロー」状態を作ることが、デジタルでは得ることのできないローテクな身体性のリラックスした状態になるということです。
これらが、本書が提唱するラクガキ効果の基本です。
インフォドゥードルの4大思考法
前述したように、本書は、ラクガキにはさまざまな効果があるとした上で、その活用の方法を具体的に紹介しています。
ここでは、ラクガキ=ドゥードルから進化して、「インフォドゥードル」と名付けられます。
「インフォドゥードル」とは、文章や音声で述べられた内容を、言葉、形、イメージを組み合わせて表現すること指す。その内容は、教科書、報告書、スプレッドシート、スライド資料、スピーチ、グループ討論などを基にしており、どこから仕入れた内容でも、ビジュアル表現によって言葉や数字を再現し、理解を深めることができる
『描きながら考える力 「ドゥードル」革命-ラクガキのパワーが思考とビジネスを変える!』p. 77
ラクガキの活用法は、4大思考法として紹介されています。
- パーソナル・インフォドゥードル (オフエア・実演やリアルタイムではない)
- パーソナル・インフォドゥードル (オンエア・聴きながら描く)
- パフォーマンス・インフォドゥードル
- グループ・インフォドゥードル
1のパーソナル・インフォドゥードルはほとんどメモの拡大版です。
自分自身で思考したり、アイデアを出したりする際に、思考の枠を広げるのに必要な方法です。
2のパーソナル・インフォドゥードル (オンエア・聴きながら描く)は、人の話を聴きながら情報を整理し、記憶を共有する方法です。
3のパフォーマンス・インフォドゥードルは、最近話題のグラフィックレコーディング、グラフィックファシリテーションに近い、視覚で記録をとっていく方法になります。
そして、4のグループ・インフォドゥードルは、グループでディスカッションしながら、何かひとつの方向に導くためのラクガキの使い方です。
ラクガクの力を活用することで、組織の力を今まで以上に発揮させ、団結力や、問題解決能力、そしてイノベーティブな企画を作り上げる方法を提案しています。
ラクガキは、個人的な楽しみから、ビジネスを生み出すクリエイティブまでさまざまな活用ができることを本書は提示をしているのです。
この書評を書かせてもらいながら、改めて絵を描く行為の大切さがわかりました。
アート思考は頭の中だけでは成立しません。
思いついたアイデアや、思いを自分の外に出して表現することとセットでなければ効果はありません。
そういう意味で、本書は絵を描くハードルを下げて、ラクガキを通して表現し、思考を深めるための指南書と言ってもいいと思います。

静岡県沼津市生まれ
武蔵美術大学 空間演出デザイン卒業
大学卒業後、3年間、世界各地で働きながらバックパッカー生活を送る。
放浪中に、多様な価値観に触れ、本格的にデザインの世界に入るきっかけとなる。
2008年株式会社カラーコード設立。
デザイン制作をするかたわら、ふつうの人のためのデザイン講座、企業研修の講師を務める。
現在は、京都芸術大学准教授として教鞭ととりつつ、アート思考を活かしたデザインコンサルティングをおこなう。